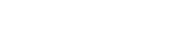ユーザーファーストのもと、人々のコミュニケーションを繋ぐLINERたち

2021年6月23日に10周年を迎えるLINE。未来に向かうGlobal LINER 12名が、LINEが誕生してからの10年を振り返りつつ、これからどう社会を変えていきたいのか、次の10年に向けた思いを語ります。
今回は、ユーザーファーストのもと、人々のコミュニケーションを繋ぐ3名のLINERを紹介します。
ユーザーのコミュニケーションを繋ぐという責任

- 入江 和孝(Irie Kazutaka)
- LINE企画センター所属。パナソニックMSE(現NTTデータMSE)、GREEを経て2014年にLINEへ入社。コミュニケーションアプリ「LINE」の企画開発に携わり、2019年に執行役員に就任。趣味はサッカー観戦。最近はテレビ観戦しかできないため、スタジアムで思いっきり応援できるようになる日を待ち望んでいる。
ーー今から10年前(2011年6月23日)にLINEが生まれました。その当時、入江さんは何をしていましたか。
入江
10年前はメーカーでAndroidスマートフォンのプロジェクトの立ち上げに関わっていました。それまで長らくフィーチャーフォン(ガラケー)の開発に従事していたため、日本の携帯電話市場がスマートフォンへ一気に移り変わっていく流れを肌で感じていました。LINEのことはその頃にテレビCMで知りました。
その後、ソーシャルゲームを運営する会社でSNSの企画開発を担当した際に、多くの企業がLINEの後を追うようにチャットアプリの開発に取り組んでいる姿を目の当たりにして、チャットが今後のコミュニケーションの中心になっていっていくんだと感じました。SNSを基盤としたサービスプラットフォームに大きな可能性を感じて、LINEでなら更にチャレンジできると考え入社を決意しました。
これまでに一番印象に残っているのは、入社間もない頃に担当した不正ログインを防ぐためのプロジェクトです。目に見える画面の改善や機能追加をしていくだけではなく、グローバルで1億9千万人の月間アクティブユーザーに安心してLINEを使っていただくために裏側の泥臭い取り組みが欠かせないことを身を持って経験しました。
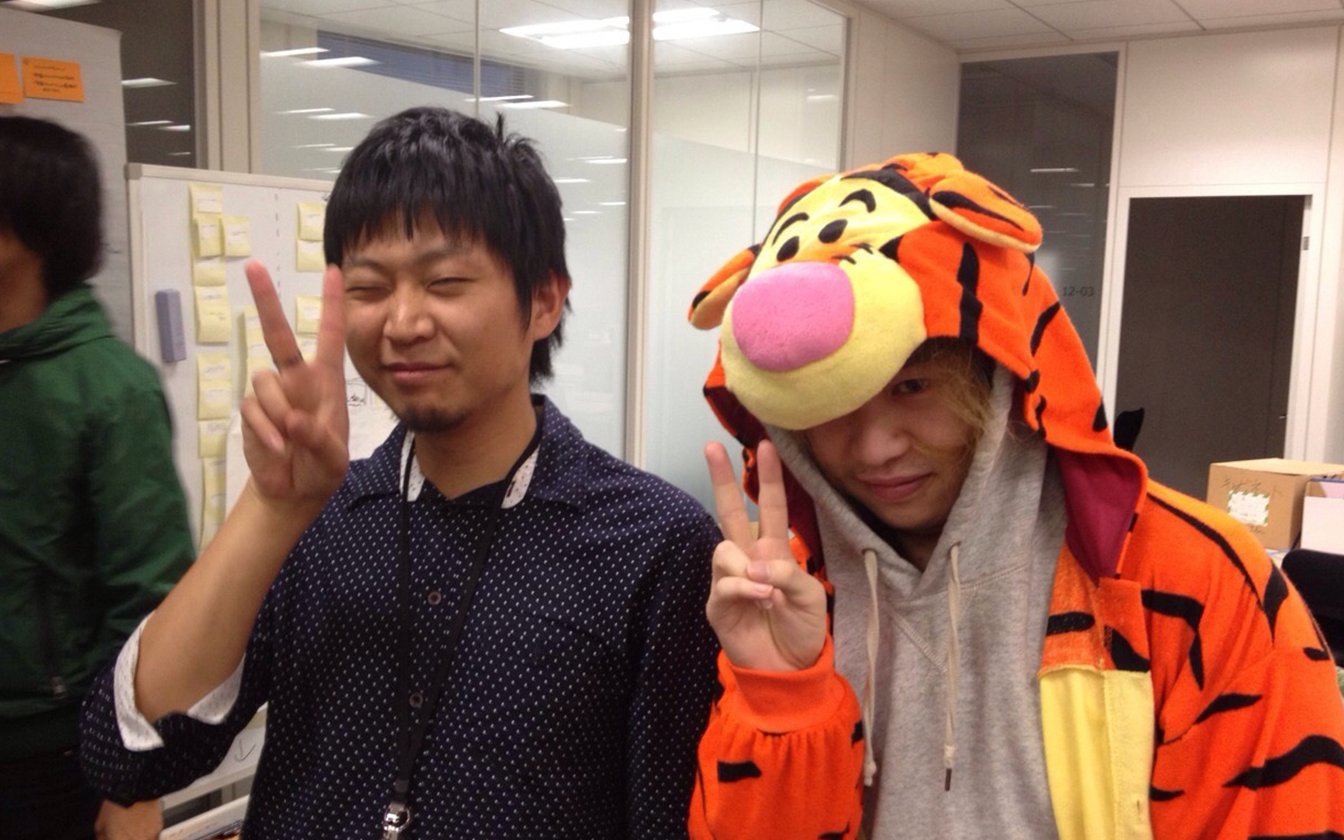
10年前の入江さん。
ーー現在のLINEの「強み」、そして対処すべき「課題」は、何だと思いますか。
入江
コロナ禍の状況のなかで、長らく会えていない友人や遠くに住んでいる家族とビデオ通話で会話ができるのはLINEの強みだと感じています。同時に、人々のコミュニケーションを支えていることへの責任や重みも感じています。一方で、様々なサービス・機能を世の中に送り出したとしても、"どういう機能か"、"何が良いのか"、"どんな場面でどう使ってほしいのか"がユーザーにはっきりと届いていないことに課題感を持っています。
今後は、「LINEでなんでもできますよ」と訴えるのではなく、生活の中で必要としているものが"自然にLINEから見つかる体験"を届けることがより求められると思っています。

ーーこれから、LINEで何がしたいですか。
入江
入社した当時、"ユーザーファースト"の視点のもと、「ユーザーにとって本当に良いものを作っていけば、売上は後からついてくる」というマインドでプロダクトづくりをしていて、これまで勤めていた企業とは全く異なる価値観だったので、カルチャーショックを受けたことを今でも覚えています。「LINEがあって良かった」と思ってくれる人が一人でも増えてくれるように、妥協せずに課題と向き合い、考え抜き、LINEというプロダクトが向かう方向性をしっかり示していければと思います。
その上で、LINEを一緒に作っている企画開発に関わるチームメンバーの能力を最大化し、チャレンジしていける環境をしっかりと作っていきたいです。
旅をしながらユーザーニーズを汲み取ってきたエンジニア

- キム ビョンチャン(Beyoungchan)
- LINE Plus Service Engineeringチーム所属。Naver Business Platform(NBP)にてインフラエンジニアとして従事した後、2013年にLINE Plusに入社。以降コミュニケーションアプリ「LINE」の安全性と信頼性の維持のためのサービスエンジニアリングを担当。趣味はスキューバダイビングと走ること。頭をすっきりさせるために毎朝のランニングが習慣。
ーー今から10年前、Byeongchanさんは何をしていましたか。
Byeongchan
10年前は、インフラエンジニアとして主にシステムで発生する障害の原因を探して解決するトラブルシューターの仕事をしていました。その中で、LINEのインフラに関する業務を担当する機会もあり、次第にインフラだけではなく、LINEのサービス全体を扱ってみたいと思うようになり、LINEへ入社を決めました。
この10年で最も印象に残っているのが、2013年ごろから数年間にわたって行った「LINE遠征隊」という仕事です。これはLINEのエンジニアと開発者が直接、ヨーロッパ諸国、アメリカ、東南アジアなど、世界中の国を訪れ、国によって異なるネットワーク状況やLINEのユーザビリティを検証するプロジェクトでした。ネットワーク環境が弱い国や地域でもスムーズにメッセージの送受信が行われるようにデータ量を減らしたり、機能を追加したりするなど、国や地域ごとの最適化を行いました。ユーザーたちに、LINEを使いながら不便に感じること、欲しいと思う機能を質問したこともありましたね。
ネットワークの進化を肌で感じたのも貴重な体験でした。例えばタイに初めて訪れた時は、ネットワークが非常に弱く、スマホで写真一枚を送るのも長い時間が必要でしたが、3回目のタイ訪問時には、空港から宿泊先までインターネットストリーミングで動画を見ながら移動できるほどにネットワークの速度が向上していて、インフラの発展に驚きました。開発者としてユーザーが実際にLINEを利用している環境を体験できたことはとてもいい経験だったと思います。
LINEのローンチ初期は、果たしてどれくらいの人たちがLINEを使ってくれるだろうという不安もありましたが、あっという間に世界中に広がり、今では当たり前のように人々の生活に溶け込んでいます。人と人との距離を縮められたことが、LINEの10年の大きな成果だと思います。

10年前のBeyoungchanさん。お子さんと一緒に遊園地へ行った時の一枚。
ーー現在のLINEの「強み」、そして対処すべき「課題」は何だと思いますか。
Byeongchan
サービスをより良くしていこうとする開発文化と、どんな時も挑戦を応援してくれる仲間の存在がLINEの強みだと思います。例えば、サーバーの障害など、何か問題が生じた時、私たちは責任の所在ではなく、原因は何なのか、どうすれば解決でき再発を防止できるかを前向きに議論し、素早く対応をします。さらにそれらの知識をストックし、今後に生かそうとする文化があります。
そして、周囲にいる同僚も、現状をよりよく変えていこうとするチャレンジを応援してくれます。だからこそより良いサービス開発に向けて共に全力を尽くすことができると思います。仲間の存在は本当に心強いです。
LINEはこれまでユーザー同士が簡単かつ無料でメッセージの送受信ができるという点で人と人をつないできました。今後はその領域をより広げることが必要と感じます。例えば、文字と音声の境界を消すこと。つまり音声を簡単に文字データにできたり、文字で送ったメッセージを音声で聞いたりすることができれば、コミュニケーションの幅はより広がっていくと思います。AIテクノロジーを活用すればそのようなサービスをユーザーが当たり前のように使うことも、近い将来可能だと思います。
究極的には国と国との境界や、言語の境界ですらLINEを通じて消すことができれば、もっと幸せな世界を作ることができるのではないかと夢見ています。

ーーLINEでこれから何をしたいですか。
Byeongchan
世界中のユーザーに愛され満足してもらえるサービスをこれからも作り続けたいと思います。「LINE遠征隊」で様々な国を訪れ、それぞれの国の環境を肌で感じながらユーザーのニーズを理解して改善に努めていた時のように、これからも、もっと多くのユーザーに満足してもらえる良いサービスを作り出すことが、私のすべきことだと思います。
もっと個人的な話をすると、新年を南の島で迎えることも私の願いです。毎年、新年のタイミングで全世界のユーザーが"Happy New Year"のメッセージをLINEで送りあうことによる大規模なトラフィック対応があるため、長らく新年をゆっくりと迎えることができていません(笑)。いつかトラフィックのことを心配することなく、優雅に南の島の波に揺られながら新年を迎えてみたいですね。
LINEは自分の最善を尽くし、仲間と一緒に価値のあるサービスを生み出せる場所だと思いますし、もっと良い場所にして、これからの10年も仲間と共にユーザーにとって役立つサービスを届けていきたいです。
「Life on LINE」へ、データからニーズの変化を感じ取る

- キム ナミル(Namil)
- LINE Plus Messaging Data Engineeringチーム。NAVERを経て、2013年にLINE Plusへ入社。LINEメッセージの送受信機能を支えるバックエンドサーバーの開発・運営を担当。現在はデータからユーザーニーズを分析し、システム開発を担当する組織をリードしている。
ーー今から10年前、Namilさんは何をしていましたか。
Namil
10年前はNAVERで働いていたころですね。大規模のシステム開発と運営に興味があり、それができる環境を求めて、LINE Plusに入社しました。
当時のLINEはメッセージ機能しかないシンプルなアプリでした。でも、現在ではフードデリバリーや支払いなども行えるようになり、国や地方自治体と連携した公共性の高い役割も担っています。ずっと成長を見てきた自分からすると不思議な気持ちです。さらには、オンライン会議の背景エフェクトやユーザーのアバターなど、コロナ禍のニーズに合わせた機能も提供しており、LINEのビジョンである「Life on LINE」に一歩ずつ近づいていると感じています。
入社してから、私個人の生活も大きく変わりました。一番の変化は、LINEを仕事でも使うようになったことです。同僚とのコミュニケーションがとても速くなり、業務がスムーズに進むようになりました。それから、プライベートでもユーザーのことを気にするようになりました。
2013年頃に、日本を旅行した時に、街中でLINEを使っている人をたくさん目にしました。自分が開発したサービスを、多くの人が実際に利用していることがなんだか不思議で、きちんとメッセージが送られているか、何か不便なことはないか、気になって仕方がありませんでした。あの時のドキドキは今でも忘れられません。
ーー現在のLINEの「強み」、そして対処すべき「課題」は何だと思いますか。
Namil
LINEの「強み」は、様々なバックグラウンドを持つ、優秀なメンバーがいることだと思います。LINEの開発部門は、同僚との協業を基盤としており、1つの機能を開発するために、ビジネスチームやフロントエンド、バックエンド、インフラなど、様々な部署との協業が必要です。海外のメンバーとともにサービスを作る機会も多いのですが、言語、文化は違っても「より良いLINEのシステムを作る」という1つの目標に向けて、情熱を持って取り組んでいると思います。共に歩める仲間の存在が、LINEの最大の武器ですね。
また、この10年の間に積み重ねた「開発ナレッジ」も私たちの大きな財産です。サービスを運営していると、入念なプロセスを踏んでいても、システム障害が発生してしまうことがあります。LINEの開発部門では、システム障害が起こった後に必ずレビュー会議を行い、原因と対策を明確にして、似たような障害を防ぐ方法を多角的に議論するようにしてきました。それを10年間、地道に積み重ねてきたことで、システム障害を防ぐプロセスが整理されて、10年前と比べて安定的にLINEを使ってもらうことができています。今後もさらに改善を続けていきたいと思っています。
「課題」としては、2つ挙げたいと思います。LINEはアジアを中心に、世界に向けてサービスを展開するグローバル企業です。1つのサービスを作るために様々な国や地域のエンジニアと協業していく必要があります。開発拠点間のコミュニケーションが円滑にならないとサービスや機能の品質が均等に維持できず、各国のユーザーに満足してもらえません。言語やバックグラウンドが違うメンバーと働くことは簡単ではありませんが、国を超えた拠点間のコミュニケーションをさらに密なものにすることが、サービスの品質を高めることにつながると思っています。
それから、LINEの機能について、いちユーザーの目線で話すと、トークルームはやや複雑だな、と感じる時もあります。LINEは、今や友だちとのトークだけでなく、仕事の連絡に使っているユーザーも多いと思います。それに加えて、様々なサービスの公式アカウントも増えているので、トークルームをパーソナライズできるようにするなど、ユーザーニーズに合わせて、シンプルでより便利な機能を提供していくことが、これからの課題だと思っています。
ーーLINEでこれから何をしたいですか。
Namil
日々状況が変化する時代で、未来を予測するのはとても難しいですね(笑)。ただエンジニアの1人として、業務で直面する様々な問題を解決するのに関心がありますし、自分の仕事の成果がユーザーの生活に少しでも役に立つといいなと思っています。そのためにも、日々の変化やユーザーのニーズにしっかりと耳を傾けていく姿勢をこれからも持ち続けたいと思っています。