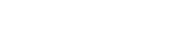グッドデザイン賞受賞! CREATIVE CENTERのリーダーに聞く「いいデザイン」創出の工夫

LINEのあらゆるデザインを生み出している組織「CREATIVE CENTER」は、2021年度グッドデザイン賞や、国際的なデザイン賞「Red Dot Award」を受賞するなど、国内外で高い評価を受けています。
CREATIVE CENTERのリーダーたちは、「いいデザイン」を生み出すために、どんな工夫をしているのでしょうか。それはデザイン領域に限らず、良質なアウトプットを生み出すための参考になるかも知れません。
冒頭写真の8人(左上から、Product Design2室のユン・ジョンゴン、Product Design1室のキム・ヨンホ、BXデザイン室のクォン・ジョンラン、中段左から、映像デザイン室の坂本亘由、センター長のキム・ソングァン、スペースデザインチームのキム・ナム、下段左から、クリエイティブコミュニケーションチームの清水久美子、クリエイティブ戦略チームの小林謙太郎)に、「いいデザイン」創出の工夫や、個人的に「WOW」(LINEの価値基準:思わず友だちに教えたくなる驚き/感動)を感じるデザインについて聞いてみました。
ちょっと、その前にCREATIVE CENTERの役割について、センター長のキム・ソングァンに聞きましたので、ご紹介しておきます。
CREATIVE CENTERの役割
CREATIVE CENTERは、国内のLINEおよびLINE関連サービスを横断して担うデザイン組織です。私たちが大切にしているデザイン哲学、「シンプリファイド(Simplified)」――シンプルにすることで、ユーザーが理解しやすくなり、ストーリーも広がり、飽きのこないデザインになる――という考え方に基づいて、デザイン技術の設計・開発・リリースを推進しています。さらに、LINEファミリーサービスがそれぞれの特徴を生かしながらも、「LINEブランド」をしっかりと伝えられるような一貫性と、デザインを経営戦略の中心に据えた「デザイン経営」を推進し、UXのベストプラクティスの創出などにも力を入れています。(キム・ソングァン)
実際には、いかにしてデザインを「シンプリファイド」(=WOWを生み出すカギ?)しているのでしょうか。まずはLINEのプロダクトとブランド体験(BX)のデザインをリードする3人に登場してもらいましょう。
Product Design1室の視点
-
回答者=キム・ヨンホ(Kim Youngho)
Product Design1室室長。新規プロダクトのプロトタイプ作成や、LDS(LINE Design System)、コマース事業、O2O事業、HR事業のデザインをリード。現在はLDS、LINEドクター、LINEヘルスケア、LINEバイト、HR新規事業に注力している。新規プロダクトのプロトタイプ作成では、プロダクトの全体的な方向性を決定するための重要なプロセスを担っている。
Q. 「いいデザイン」を生み出すために、特に意識していることは?
ヨンホ
いくら、いいデザインを作ろうとしても、全てを完璧にして、あらゆる人を満足させることは、ほぼ不可能だと思います。いくらトレンドが反映されているデザインでも、私だって「なぜ?」と思う部分があります。この辺りは、デザイナーの個性にも関わる領域です。
これまでの自分の経験や視覚的なセンスをメインにしながらも、ユーザーにとって使いやすい最低限の基準を必ず守るようにしています。
Q. 普段から、良質な情報をインプットすることも大事そうです。インプットで心掛けていることはありますか。
ヨンホ
トレンドの変化を感知して、多様な情報をインプットすることももちろん重要ですが、そこから自分のデザイン的なセンスが上がったと感じたことはありません。
むしろ、とても日常的なところからインスピレーションを得て、自分の中に何らかの変化が起きることの方が多かったと思います。静かな原宿の裏通り、夕焼けの前の富士山、印象深かった映画や音楽......のようなものからです。
Q. 個人的に「WOWを感じるデザイン」や「好きなデザイン」を教えてください。
ヨンホ
具体的な例を挙げるなら、デザイナーの中村ヒロキさんが展開する「visvim」というアパレルブランドは、ディテールが優れたデザインという部分によくマッチすると思います。
初めてこのブランドを見た時、伝統的なデザインと現代的なデザインを適切にミックスしながら、ユニークに表現している部分にとても驚きを感じました。メインとなる服はもちろん、店舗の雰囲気、ロゴデザイン、ウェブサイトまで、デザインに一貫性を感じます。このブランドならではのユニークなカラー表現から、たくさんインスピレーションを得られました。
Product Design2室の視点
-
回答者=ユン・ジョンゴン(Yoon Jeongkwon)
Product Design2室室長。Fintech事業、Local Place事業、マッチング事業のサービスのUIデザインをリード。担当サービスは、LINE Bank、LINE証券、LINE FX、クーポン、マイカード、ポケットマネー、LINE PLACE(LINE CONOMI)、LINEレシート、トーク占いなど。クイックな更新を繰り返して、改善を続けていくアジャイルな手法で、各事業の「サービス企画」と「開発」を接続する大切な役割を担っている。
Q. 「いいデザイン」を生み出すために、特に意識していることは?
ジョンゴン
ユーザーが「シンプルに感じるか」という点です。シンプルなユーザー体験を提供する。つまり、最短経路でユーザーが望むものを得られて、明確に認知でき、意識の流れに沿って自由にサービスを使えるようにすることです。
UIにとって「いいデザイン」とは、「全ての要素がコンテキストを含み、明確な目的や意図によって定義されているもの」だと思います。そのため、デザイナーはより明瞭で理解しやすい、シンプルなユーザー体験を常に意識しています。
Q. シンプルを目指す上で、どうやったら上手く、自分たちが意図したコンテキストを感じさせることができるのでしょうか。
ジョンゴン
アウトプットに対して、レビューを進行するときに「Why」という疑問を絶えず投げかけています。「機能の定義」についての質問から、「ゴールは何なのか」「企画内容に問題ないか」などの大きなカテゴリの質問だけでなく、「どんな意図でデザインしたのか」を非常に細かい要素まで、しつこく掘り下げるようにしています。
結果的に、意思決定者の思いつきや個人的な感覚に依存せず、論理的な思考をベースにデザインの意思決定ができますので、重要なプロセスの1つだと思います。
Q. 個人的に「WOWを感じるデザイン」や「好きなデザイン」を教えてください。
ジョンゴン
長い時間を経ても通用するデザインが好きです。ただ実務では、自分の好みとプロジェクトの方向性が混ざらないように、好きなデザインと優れたデザインは、頭の中で分離させて置くべきだと思っています。「好きなデザイン」は100%好みの話になりますので、業務とはあまり関係ないですね。
業務では速いスピードで変わっていくトレンドを把握し、未来を予測しながらデザインを考えなければならないので、クラシックなデザインに触れると、心に安らぎを感じます。
例えば、「The New York Times」のアプリを開いて、よく整理されたタイポグラフィとレイアウトを見ると、気分が良くなります。でも、基本的に私は「好きなデザイン」≠「WOWなデザイン」だと考えています。
WOWを感じたデザインを挙げるなら、2016年のInstagramのデザインリニューアルから、多くのインスピレーションを受けました。ブランドとアプリのデザインが一緒にリニューアルされた事例です。
アイコンはコアバリューだけを残し、非常に単純にまとめられ、UIも最小限のカラーを使用して簡素化され、ユーザーのコンテンツがより引き立つように設計されています。
たくさんのファンがいるサービスのデザインを大幅に変えるのは大変なことです。Instagramのリニューアルは、当初たくさんの反対意見や不満の声が上がりましたが、長い時間が経つにつれ、ユーザーが慣れていき、最終的に正しい方向に進化したことを証明しました。
ぜひ、デザインリニューアルをリードしたイアン・スパルタ―の記事やNetflixのドキュメンタリー番組で、エキサイティングなストーリーの詳細をチェックしてみてください。
BXデザイン室の視点
-
回答者=クォン・ジョンラン(Kwon Jungran)
BXデザイン室室長。各サービスのブランドやブランドを通じた体験設計を担当。サービスのロゴやアイコン、様々なイベントのノベルティなど、主にオフラインのクリエイティブに携わる。広い意味でLINEのブランドアイデンティティを担う組織をリードしている。通称はRanさん。
Q. 「いいデザイン」を生み出すために、特に意識していることは?
Ran
世の中には、いいサービスブランドやデザインが溢れていますが、ブランド哲学を人々の心に刻み込むには、シンプルで直感的なコミュニケーションが重要です。
Never different! But always change! ―― 時代によって絶えず変化しながらも、基本を失わないブランドの進化形態をWOWな前例として見ていきたいです。
Q. 個人的に「WOWを感じるデザイン」や「好きなデザイン」を教えてください。
Ran
ディーター・ラムズ(インダストリアルデザイナー)の「グッドデザインの10原則」は、私が追求するデザインの方向性と完全に一致しています。
「いいデザイン」は、分かりやすくシンプルで、実用的でなければなりません。持続性がなく、分かりにくさを取り繕うために説明を付け加えたデザインは、その真逆にあたります。
グッドデザインの10原則
- 革新的
- 実用的
- 美しい
- 分かりやすい
- 主張しない
- 誠実である
- 長持ちする
- 細部まで完璧
- 環境にやさしい
- 純粋で簡素
(「Vitsœ」公式サイトより)
様々な情報がフィルタリング無しで織り込まれたデザインに触れた時、私たちは疲れを感じます。机の上が散らかっていたら、イライラしてしまうような感じです。そんな時は、デザインを通して伝えたい言葉を、少しだけ減らしてみましょう。本当に伝えたいコアバリューだけを簡潔に表現すれば、機能と感性を両立させたデザインが創造できます。
いいデザインは、時を経ても変わらずに輝いています。自分のデザインが、将来的にどんなブランドのモチーフになったら、意義を感じるでしょうか。もしそれがAppleのようなブランドだったら「WOW」ですよね。
ディーター・ラムズの計算機が、iPhoneのアプリにインスピレーションを与えたことは、時代やメディアを超えて、いいデザインにつながったWOWの好例だと思います。
CREATIVE CENTERには、映像や空間をデザインする専門チームも存在します。映像、空間デザインの視点からも話を聞いてみましょう。
映像デザイン室の視点
-
回答者=坂本亘由(Sakamoto Nobuyuki)
映像デザイン室副室長。LINEに関わる映像や写真、インタラクションなどのメディアを制作するチームをリード。主にマーケティングやブランディングにまつわるイベント、SNSなどの映像を通して、LINEの理念やサービスの利便性を最大化し、ユーザーに届ける活動をしている。(参考:「LINE Japan」のYoutubeチャンネル )
Q.「いいデザイン」を生み出すために、特に意識していることは?
坂本
デザインはコミュニケーションだと思っているので、「映像を観た人がどう感じるか」「観た後でどんな態度変容が起こるのか」を常に意識しています。
映像の仕事に応用できる考え方としては、「人間万事塞翁が馬」という言葉です。中学生で習う故事成語ですが、映像も、自分で正しいと思っていたことが、誰かの全く違う意見でとても良い結果になることが多々あり、制作の過程で色々悩んだ際には、一喜一憂せずに多角的に意見を取り入れて、ベストなものを作っていこうと心掛けています。あと、視野角や視点の導線、色彩の捉え方、情報の処理速度など、認知心理学の観点は映像デザインにとってとても有益です。
Q. 個人的に「WOWを感じるデザイン」や「好きなデザイン」を教えてください。
坂本
「これだ!」と1つに絞るのは非常に難しいですが、有名どころを挙げると、クリス・カニンガム、スパイク・ジョーンズ、ミシェル・ゴンドリーの作品は、DVDが壊れるぐらい何度もループして観ていました。
また、映像とデザインの関連性を明確に意識させてくれたのは、高校生の頃に観たカイル・クーパーのタイトルバックの作品集だと思います。
関連リンク
Design Legends-- Kyle Cooper Main Title Designer PT 1 (Braveheart, Se7en, Dawn of the Dead)
Q. 他にも具体例があれば、教えてください。
坂本
■SONY「Bouncy Balls」
10年以上前に制作されたSONYの広告です。当時はYouTubeもまだ流行っておらず、このような実証系の挑戦的な映像も広告で消化されていました。「25万個のスーパーボールをサンフランシスコの坂の上から一気に放つ」という、とてもキャッチーな企画ですが、企画の強さだけではなく、撮影手法や音楽、編集、どれを切り取っても完成度が高い作品です。特に、作中に有機的なモチーフを入れた演出力と、そのモチーフをカエルにしてしまう発想力は素晴らしいと思います。
■GEICO「Unskippable」
2015年のカンヌ広告賞でグランプリを受賞した、GEICOという自動車保険会社の広告です。最近のカンヌは総合力で評価される傾向なので、このように純粋なクリエイティビティだけで評価された作品は、今となっては珍しいかもしれません。TrueView広告におけるスキップ問題を、情報デザインとクラフト、そして笑いによって見事に解決しています。
スペースデザインチームの視点
-
回答者=キム・ナム(Kim Nam Woo)
スペースデザインチーム マネージャー。LINEのオフィス空間を設計、デザインするチームをリード。LINER(LINE社員)にとって最も相応しく、LINEの様々な成長につながるワークプレイス作りを目指している。
Q. 「いいデザイン」を生み出すために、特に意識していることは?
ナム
空間デザインの最も大きな特徴は、空間を作った時点で完成ではなくて、実際にユーザーに使ってもらって完成すること、時間をかけて完成に向かっていくことだと考えています。ですので、作る時点で「これはこうだ」と決めつけるより、「このようなことがありそう」など、いろんな方向性を考えながら、デザインするように意識しています。使う人や組織によって、空間のニーズは変わってきますので、可能な限り多くのニーズに対応できる空間を目指しています。
Q. 個人的に「WOWを感じるデザイン」や「好きなデザイン」を教えてください。
ナム
全体的な完成度が高い空間はたくさんあると思いますが、細かく見てみると普通だったりして、がっかりすることが多いです。私が好きな空間は「大半の人が気付かない部分まで深く考え、計画、デザインされている空間」です。
木とコンクリート、2つの素材で素晴らしく構成されており、木の廃材なども内部のデザインに活用していたり、コンクリートの目地など、非常に細かい部分まで完成度が高い建物。また、大げさ過ぎず、内部空間の使われ方を考え、シンプルに構成されている点も面白い。
■Amazon Fashion Imaging Studio
Amazonの写真や動画を撮影するスタジオ。もともと倉庫だった建物をリノベーションした事例です。既存の建物を最大限活用しながら、空間の使われ方を考慮して、カーテンなどで区画を構成しているところが印象的です。
-----------
「いいデザイン」を生み出すためには、働く環境や、組織作りも大切だと思います。その辺りを担当しているチームにも話を聞いてみます。
クリエイティブ戦略チームの視点
-
回答者=小林謙太郎(Kobayashi Kentaro)
-
クリエイティブ戦略チーム、マネージャー。「LINEのクリエイティブと世の中のクリエイターとの距離を縮めること」をミッションに、CREATIVE CENTERの組織戦略の企画業務、採用や社外PRの企画プロデュース、イベント登壇業務などに従事している。通称はkenny。(参考:クリエイティブセンターに新しく生まれた「組織そのもののデザインチーム」と"中の人たち" )
Q. ご自身が考える「いいデザイン組織」とは?
kenny
ユーザーに愛されるものをつくるのが、デザイナーの使命だと思っているので、そういう意味でCREATIVE CENTERは「いいデザイン組織」だと思います。常にユーザーをど真ん中に置いて、真摯にデザインに取り組んでいる姿勢は本当に頼もしいですし、多くの方に知っていただきたいです。
Q. ご自身が生み出そうとしている「WOW」とは?
kenny
役割としては「生み出す」というより、LINEに既に存在したり、新たに生まれたWOWを「伝えていく係」だと思っています。それこそ、CREATIVE CENTERがつくるものや、組織自体がWOWであり、そのことを多くの人に知っていただくことで、WOWを感じてもらえたらと思います。では、なぜ伝える係が必要かというと、以下の課題があるためです。これらを改善するためにチャレンジを続けております。
認知の課題:そもそも、CREATIVE CENTERが知られていない。
誤解の課題:CREATIVE CENTERでは、メッセンジャーをつくっていると思われている。
評価の課題:ユーザーが何も意識せずに使えるデザイン=何も感じないデザイン=LINEのデザイン?
Q. 課題に対して、どんな取り組みをしているのでしょうか。
kenny
例えば、「認知」においては広告を出したり、デザイン系・他社開催のイベントに登壇したり、SNSなどで向上を図り、「理解向上」という点では、例えば、そのイベントの中で「CREATIVE CENTERや、その中のデザイナーは何をする人ぞ」という話をしたり、noteで特集記事を書いたり。
「評価」に関しては、より専門的な話になってくるので、現役のデザイナーにイベントで語ってもらったり、第三者視点という意味で雑誌やウェブメディア等で、サービスやブランドの詳細を紹介する記事を書いてもらったりしています(参考:元GoogleのデザインリードがLINEデザイン組織のトップに 金善琯さんのデザイン組織論とは )。
クリエイティブコミュニケーションチームの視点
-
回答者=清水久美子(Shimizu Kumiko)
クリエイティブコミュニケーションチーム、マネージャー。センター内の組織運営、デザイナーの教育支援、業務サポート、SNS運営など、様々な課題をコミュニケーションで解決し、世界に通用する組織文化の構築を目指している。アイデアコンペ「20% idea project」や年末アワード「Creative Center ON」など、センター内イベントの企画、運営もリードする。
Q. ご自身が考える「いいデザイン組織」とは?
清水
組織は個々の集まりなので、やはり、個々の幸福度が高いことが、いい組織につながるのではないかと思います。どれだけ個々が満足しているか、楽しんでいるか、幸せか。
1日の中で仕事をしている時間が1番長いですよね?1番長い時間を費やすのであれば、楽しくないともったいないですよ!いやいや仕事をするなら、辞めることも1つの選択肢なのかもしれません。幸せを感じられないなら、もっと幸せになれる方法を考えるべきです。自分は幸せか?自分が幸せになる方法は?常に自問自答して欲しいと思います。
自分が幸せであれば余裕ができます。そうすれば、自然と周りに目が行き、周りにも愛情を注ぐことができるようになるのではないでしょうか。相手を思いやる気持ちが生まれませんか?そうやって、良い組織が構成されていくんじゃないかと思います。Love yourself♡
-----------
最後に、センター長のキム・ソングァンにも、同じような質問をしてみました。
Q. 今後、CREATIVE CENTERをどんな組織にしていきたいか、「CREATIVE CENTERの未来像」について聞かせてください。
ソングァン
CREATIVE CENTERの大きな役割は、問題を解決するために「より良いデザインを追求すること」「普遍的なデザインで解決策を提示すること」です。デザインを創ることはもちろん、そのデザインを通して、サービスや事業、ユーザーの課題を解決し、LINEのミッションである「CLOSING THE DISTANCE」を推進することが求められています。ただ美しくて、目新しいものを創るのではなくて、課題を解決するために、誰よりもユーザーの視点から物事を考えて、いいアイデアを創出するデザイン組織を目指しています。
それともう1つ、私たちは4つのC(=Competency、Change、Challenge、Competitiveness)をスローガンとして掲げており、中でも「Challenge」に特に重きを置いています。変化を捉えることも重要ですが、より挑戦することが大切です。私たちは事業領域ごとに組織を明確に区分し、それぞれの事業に対する深い理解と専門性、強い責任を持つ構造に変わりました。これにより、変化を素早くキャッチアップして、デザイナーの立場から事業やサービスをリードし、個人としても挑戦しながら、事業やサービスの挑戦を支えられる組織でありたいと考えています。
私たちは組織環境の整備や様々な支援を通して、「世界中のデザイナーが仕事をしたいCREATIVE CENTER」になれるようベストを尽くしたいと思っています。
-----------
今回はCREATIVE CENTERのリーダーたちに、それぞれの視点から「いいデザイン(組織)」を生み出すための工夫について、コメントしてもらいました。「シンプルにする」「重要なモノから1つずつ」など、デザイン領域に限らず、クリエイティブな仕事をする上でのヒントが散りばめられていたように思います。1フレーズでも、皆さんの仕事の役に立てば幸いです。
また、興味がありましたら、下記のリンクも見てみてください。
CREATIVE CENTER関連リンク